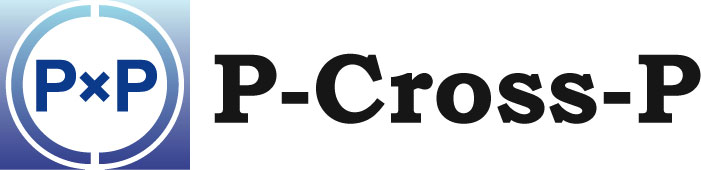シュタットベルケの源流と系譜
ドイツのシュタットベルケについて、ChatGPT(Deep Serch)で調べてみました。
質問 ドイツのシュタットベルケの起源からその後の経緯と現状について、エポックとなる事例等を含めて俯瞰的にまとめてください。
ChatGPT:
シュタットベルケ:歴史と現代的展開
1. 19世紀におけるシュタットベルケの起源(ガス事業の発端)
シュタットベルケ(Stadtwerke)は、都市が主体となって地域の公共サービスを提供する事業体であり、その歴史は19世紀にまで遡ります。産業革命期、ドイツの都市では人口が急増し、夜間照明や上下水道などインフラ需要が高まりました。はじめは民間企業が都市と契約してガス灯による照明や水道整備を担いましたが、19世紀後半になると多くの都市がそれら事業を「公営化」し始めました。この動きは「自治体社会主義」とも呼ばれ、公共の福祉のために都市がインフラ事業を直接運営する潮流でした。例えばベルリンでは、私営水道会社のサービス不備に市民の不満が高まり、1873年にベルリン市がその水道会社を買収して公営化しています。こうした経緯から、19世紀末までにガス供給や水道といった都市サービスは次第に自治体による運営へ移行しました。
19世紀中頃には早くも最初期のシュタットベルケが誕生しています。例えば1840年、ライプツィヒでは「ガス照明会社」が設立され、市内約2,000灯の街路照明にガスを供給しました。その後、1880年代以降には電力インフラが登場し、街路や家庭の照明に電気を導入する都市も現れました。ガスや水道は多くの都市で自治体管理となっていきましたが、電気事業に関しては当初民間企業が重要な役割を果たし、都市と契約して発電・供給を行うケースも見られました。それでも20世紀初頭までには、市営の発電所や電力ネットワークを持つ都市も増え、路面電車など公共交通への電力利用も広がりました。1900年代初めには、ドイツ全土で水道事業の94%が自治体運営となり、ガス・電気も含め「都市の事業」としてのシュタットベルケが各地に定着していったのです。
2. 帝政期からワイマール期、ナチス時代、戦後復興期における変遷
帝政期(1871~1918年):ドイツ帝国期には、多くの都市がシュタットベルケを通じて都市インフラの整備を進めました。帝国の成立(1871年)以降、都市の自治権が強化され、上下水道やガス・電気供給、路面電車などを市が主体的に運営する動きが広がりました。20世紀初頭までに、シュタットベルケは地域独占的な公共事業体として各都市に根付き、衛生の改善や産業振興に寄与しました。都市によるインフラ整備は「生存必需品の確保(Daseinsvorsorge)」という理念にも支えられており、基本的な生活インフラを住民に安定供給することが自治体の責務と考えられました。一部の大都市では、近隣自治体を合併して都市圏を拡大し、公営事業を統合する試みも行われています。例えば1920年のベルリン大都市法では、新たに編入した郊外地域も含めて電気・ガス・水道事業をベルリン市が一元的に運営する体制が築かれました。これにより都市圏内で料金やサービス水準を標準化し、不採算地区にもサービスを行き渡らせることが可能になりました。帝政末期からワイマール初期にかけて、こうした都市間連携や公営事業の統合が進み、シュタットベルケは都市近代化の尖兵として機能しました。もっとも、第一次世界大戦後のインフレや財政難により設備投資が滞るなどの課題も抱えていました。
ナチス時代(1933~1945年):1930年代にナチス政権が成立すると、公共事業の統制と再編が進められました。1935年にはナチス政権下で最初の「ドイツ市町村法(Gemeindeordnung)」が制定され、自治体の経済活動に関する基本原則が定められます。この法律ではシュタットベルケの運営について、「公共目的」(公益性)に沿うこと、自治体財政の健全性を損なわないこと、そして民間企業を不当に圧迫しないこと(補完性の原則)といった条件が明文化されました。ナチス政権は戦時体制への移行に伴い、エネルギー事業の組織改編や規制強化にも乗り出し、大規模発電所や送電網の統合を推進しました。一方で、都市ガス・水道など地域レベルの公益事業そのものが国有化されることはなく、従来のシュタットベルケは形を変えながら存続しました。ベルリンでは1930年代後半にかけて市が民間の電力会社の株式を段階的に取得し、電力会社(ベヴァグ)の完全な市営化を達成しています。このようにナチス期でも表向きは「再公営化」による市営事業の統合が進みましたが、その目的は本来の市民福祉ではなく戦時動員や国家政策に沿ったもので、公営事業もナチスの統制下に置かれたと言えます。総じてナチス時代、シュタットベルケは国策に組み込まれつつ、公営・民営の混在した独特の形態で公共サービスを提供し続けました。
戦後復興期(1945~1950年代):第二次世界大戦後、ドイツのインフラは大きな被害を受けましたが、戦後復興とともにシュタットベルケも再建されました。連合国統治下、西ドイツ(のちの連邦共和国)ではイギリスやフランスなど他国のような大規模国有化は行われず、戦前から存在した地域の公営事業体が引き続き重要な役割を担いました。1949年制定のドイツ連邦共和国基本法(憲法)第28条では自治体の自治権が保障され、地方公益事業を運営する権限も各自治体に認められました。これにより、西ドイツ各地の都市は戦後も自前のシュタットベルケを基盤に、水道・ガス・電気といった生活インフラの安定供給に努めました。一方、東ドイツ(旧ドイツ民主共和国)では社会主義体制の下、エネルギーや水道は国有の企業体制に組み込まれ、地方自治体の役割は限定的となりました。東西で対照的な道を辿りましたが、統計的には戦後もドイツ全体で見れば大半の都市が何らかの公営事業体を保持し、復興期の経済成長を支えるインフラ供給に寄与したといえます。西ドイツでは1950年代の“経済奇跡”と呼ばれる高度成長の中、電力・ガス消費が飛躍的に伸びましたが、都市ごとのシュタットベルケがこれに対応し、送配電網やガス管の拡充、新規発電所の建設などを進めました。こうした戦後復興期を経て、シュタットベルケは「戦前から続く都市の公共サービス提供者」として復活・強化されたのです。
《主要な歴史的節目(年表)》 – 19世紀から20世紀半ばまでのシュタットベルケに関する主な出来事を以下にまとめます。
- 1840年:ライプツィヒでガス事業会社が発足(市内約2千のガス灯に燃料供給)。ドイツにおける都市インフラ事業の草分け的存在。
- 1873年:ベルリン市が民間水道会社を買収し、水道事業を公営化。公衆衛生向上のため大都市がインフラを直接管理した例。
- 1890年代:ドイツ各地で「自治体社会主義」の潮流が高まり、都市のガス・水道事業の大半が市営化。
- 1935年:ナチス政権下でドイツ市町村法が制定され、自治体公企業の公共目的・財政健全性・補完性の原則が確立。都市公営事業の活動範囲に法的枠組みが与えられる。
- 1949年:西ドイツ基本法第28条で自治体の自治権を保障。戦後の西ドイツにおいて、シュタットベルケが引き続き自治体の任務として位置づけられる基盤となった。東ドイツでは同時期にインフラ事業が国有化され、地方公営事業は一旦消滅。
3. 戦後の経済成長期における公共サービスとしての位置づけと役割
第二次大戦後の西ドイツでは、経済成長とともにシュタットベルケの役割も拡大しました。1950年代から1970年代にかけての高度成長期、各都市の公営事業者は急増する需要に応えるべくインフラ整備を推進しました。電力・ガス・水道・地域暖房といったライフラインの整備は、地方自治体の使命「生活必需品の確保(Daseinsvorsorge)」として位置づけられ、シュタットベルケはその担い手となりました。多くの都市ではシュタットベルケが地域独占的に電気・ガスを供給し、その収益で上下水道や公共交通など必需サービスを維持するといった「クロスサブシディ(内部補助)」が行われました。実際、シュタットベルケは一体的・総合的にインフラサービスを運営することで規模の経済を生かし、利益部門の余剰で赤字部門を支える経営を展開しました。これは**クヴェアバンド(Querverbund)**と呼ばれるドイツ独特の公営企業モデルで、例えばエネルギー事業の利益で公共交通やプール、劇場などの不採算公共サービスを賄い、市民へ幅広いサービスを適正価格で提供することに寄与しました。こうした仕組みにより、高度成長期のドイツ都市では公共サービスの質と普及率が飛躍的に向上しました。
戦後経済成長期にはまた、シュタットベルケを取り巻く産業構造も特徴的でした。全国規模ではRWEやE.ON(前身はプレussenエレクトラやバイエルンヴェルク等)、EnBW、Vattenfall(旧ベルリンBEWAGやハンブルクHEWが統合)といった大手電力会社が発電・広域送電を担い、各都市のシュタットベルケはこれら大手から電力を購入して配電・小売りする形態が一般的でした。一方で都市ガスについては、各都市がガス会社を所有し近隣のガス田や輸入ガスを供給するケースも多く、水道はほぼ完全に自治体運営でした。このように戦後のドイツでは、大手公益企業と地域シュタットベルケが分業・協調する混合システムが成立しており、市場経済と公的サービスのバランスを取る体制が構築されていました。
しかし、1970年代以降になるとオイルショックや経済停滞もあり、自治体財政が圧迫され始めます。1980年代から1990年代にかけて、西ドイツ(および再統一後のドイツ)では、新自由主義的な政策潮流の中で公企業の民営化が議論されました。多くの自治体で財政再建策として、公営事業(シュタットベルケ)の一部または全部を民間企業に売却したり、業務運営を委託したりする動きが生じています。例えば一部の都市では、シュタットベルケを株式会社化して株式の49%を民間エネルギー企業に譲渡する、あるいは運営権を一定期間民間会社に委ねるといった手法が取られました。こうした部分民営化により、一時的に自治体収入を得る例もありましたが、その反面、公営事業の利益が民間株主に配分されるようになり地域に還元されにくくなる、経営の公共目的より収益性が優先される、といった懸念も生じました。実際、1990年代までにベルリンやハンブルクなど大都市を含め、いくつかの都市でエネルギー事業の株式が民間資本に渡り、シュタットベルケが「民間との合弁会社」と化すケースも見られました。このように、戦後の経済成長期を通じて重要な公共サービス提供者であったシュタットベルケですが、1990年代末までにその純粋な公営性は揺らぎ始め、次のエネルギー自由化時代への転機を迎えることになります。
4. エネルギー自由化(1998年)以降の再公営化や新規設立の動き
1998年、EU指令に基づきドイツの電力・ガス市場が全面自由化され、長年続いた地域独占体制に競争原理が導入されました。このエネルギー自由化により、従来各都市で安定的に営業していたシュタットベルケは、大手エネルギー企業や新規参入事業者との競争にさらされることになりました。当初、規模の小さい地方公社は資本力で劣り、政治的思惑に左右されやすいため競争に敗れるだろうとの予測もありました。実際、自由化直後の数年間で、大手エネルギー企業が各地のシュタットベルケに資本参加し、統合・買収を進める例が相次ぎます。一例として、ベルリンのガス会社GASAGはE.ONやフランスのGDFスエズ(現エンジー)などに株式を売却し民間合弁化しましたし、ハンブルクでも電力・ガス・暖房の公社(HEWなど)がスウェーデンのヴァッテンフォール社に吸収されました。こうした再編の結果、一時期ドイツのエネルギー小売市場はE.ON、RWE、EnBW、Vattenfallの「四大企業」による寡占が強まり、シュタットベルケの存在感は相対的に低下したかに見えました。
しかし、自由化から数年が経つと状況に変化が現れます。多くのシュタットベルケは地元顧客からの信頼や柔軟な経営で踏みとどまり、逆に大手が独占していた市場に挑む動きを見せました。また、ドイツ再統一後に東ドイツ各地で新設されたシュタットベルケは、自由化によって大手の寡占支配が進むことに危機感を持ち、自治体主導でエネルギー事業を守る努力を続けました。東ドイツではベルリンの壁崩壊後、1992年の連邦憲法裁判所の和解決定により自治体が地域の電力・ガス資産の権利と独自の公益事業を設立する権利を認められた経緯があり、1990年代に各地で新たなシュタットベルケが数多く立ち上げられました。自由化後もそれら新興の公社が地元で奮闘し、エネルギー供給の多元化を図ったのです。
2000年代に入ると、エネルギー市場では意外なトレンドが顕在化しました。それは「再公営化(Rekommunalisierung)」とも呼ばれる現象で、自治体が民営化した事業を再び公的な手に取り戻す動きです。自由化後の競争でエネルギー価格が上昇したことや、大手民間企業の経営効率優先が地域の環境・サービスに必ずしも合致しなかったことから、住民や自治体がエネルギー事業の主導権を取り戻そうとする機運が高まっていきました。実際、2007年以降、多くの自治体で電力・ガス配電網の運営権契約(コンセッション)が満了を迎えるタイミングに合わせて、更新入札に民間ではなく自治体公社を参入させ、事業を奪還するケースが増えました。また、新規にシュタットベルケを設立する自治体も相次ぎました。その結果、2000年以降ドイツでは150を超えるシュタットベルケが新設され、全国の公営事業体数は約900社にまで増加しています。これは自由化開始時と比べ明らかに増加傾向であり、地方自治体がエネルギー供給に改めて乗り出したことを示しています。
この流れを象徴する出来事として、**ハンブルク市の再公営化住民投票(2013年)**が挙げられます。2013年9月、ハンブルク市では電力・ガス・地域暖房の配電網を民間会社から買い戻すべきかを問う住民投票が実施され、50.9%の市民が再公営化に賛成票を投じました。これを受け、市当局はエネルギー大手ヴァッテンフォール社等との交渉により、数年かけて電力・ガス事業子会社の株式を100%取得し、公営化を完了させました。電力送配電網については6億1000万ユーロで買収が行われ、2019年までにハンブルク市の完全子会社が運営権を取り戻しています。この再公営化により、ハンブルク市は発電から送配電・小売までエネルギーバリューチェーンをカバーする公社グループを再構築し、以後、市の裁量でエネルギー政策を進める基盤を得ました。ハンブルクの例は全国的にも大きな影響を与え、その後ベルリンでも同様の住民投票(2013年に実施、僅差で不成立)が行われるなど、各地で「我が町のエネルギーを我が手に」という動きが広がりました。
このように1998年の自由化以降、シュタットベルケは一時期逆風に晒されながらも、2000年代後半からは再評価されるようになりました。競争環境で生き残った公社はサービス向上と経営効率化を進め、一方で自治体や市民は安定供給や持続可能性の観点から公営事業を見直しました。その結果、シュタットベルケは数・重要性ともに再び増大し、エネルギー供給における地方分散型の担い手として脚光を浴びています。
《主要な歴史的節目(年表)》 – エネルギー自由化前後から現在に至るまでのシュタットベルケに関する主な出来事をまとめます。
- 1992年:再統一後の東ドイツで、自治体が旧国営エネルギー資産の権利を取得し独自公社を設立することを連邦憲法裁判所が承認。東部各地で新シュタットベルケが発足し始める。
- 1998年:電力・ガス市場の全面自由化施行。既存シュタットベルケは大手企業との競争に直面し、民間資本による買収・統合が進行。
- 2005~2015年頃:自治体によるエネルギー事業再公営化の動きが顕在化。2007年前後からコンセッション回収や新規公社設立が増加し、2000年以降で150超の新シュタットベルケ創設。
- 2009年:E.ONが子会社トューガ(Thüga)を全国のシュタットベルケ連合に売却。約50の自治体が共同出資して取得し、自治体連合による最大規模のエネルギー会社が誕生(年間を通じた再公営化の象徴的事例)。
- 2011年:福島原発事故を契機にドイツ政府が脱原発・再生可能エネルギー拡大政策を加速(Energiewende)。地方でも再エネ推進の機運が高まり、シュタットベルケがその実行主体として期待されるようになる。
- 2013年:ハンブルク市の住民投票で電力・ガス・暖房の配電網再公営化が可決(約50.9%賛成)。同年、ベルリン市でも電力網公営化の住民投票が行われるも成立要件に僅かに届かず(賛成約83万票、約24.1%の投票率で不成立)。
- 2019年:ハンブルク市が電力・ガス・暖房3事業すべての完全公営化を達成。電力網買戻し費用は約6億ユーロ。再公営化後、ハンブルク公社は利益を上げ、市のエネルギー政策(石炭火力削減・水素導入など)の中核的役割を果たす。
5. 再生可能エネルギーや持続可能性と絡めた現代的な展開
近年、ドイツのシュタットベルケは気候変動への対応や持続可能な地域づくりの文脈でも重要なプレーヤーとなっています。ドイツ政府が進める「エネルギーヴェンデ(エネルギー転換)」、すなわち再生可能エネルギーへの大規模シフトと脱炭素化において、地方の市営事業体であるシュタットベルケが果たす役割は小さくありません。多くのシュタットベルケは従来の化石燃料依存から脱却するため、自ら再生可能エネルギー電源を開発・調達し、地域でのクリーンエネルギー供給を拡大しています。例えば南ドイツのシュヴェービッシュ・ハル市のシュタットベルケ (Stadtwerke Schwäbisch Hall) は、比較的小規模な事業体ながら早くから再生可能エネルギーとコージェネレーション(熱電併給)への転換を進め、2012年時点で市内消費電力の約60%を自社の分散型エネルギー(CHPプラント約30か所によるガス・バイオガス発電など)で供給するまでになりました。この実績により同社は「年間最優秀エネルギー自治体」に選出されるなど、地方エネルギー転換のモデルケースと評価されています。
ドイツ全国を見ても、シュタットベルケの多くが再生可能エネルギー事業に関与しています。2013年時点の調査で、約1,400社あるシュタットベルケのうちエネルギー事業に携わるものは約900社、そのうちの60%近くが何らかの再生可能エネルギーに取り組んでいると報告されています。具体的には、陸上風力発電所や大規模太陽光発電、バイオマス発電設備への出資、地域のバイオガスプラント運営、廃棄物焼却によるエネルギー利用、小水力発電の開発など、多岐にわたります。また、再エネと親和性の高い熱電併給(CHP)プラントを導入して発電効率を高める動きも盛んです。シュタットベルケ・シュヴェービッシュ・ハルのように、自社の売上に占める再エネ電力比率を大幅に引き上げた例もあれば、ミュンヘンやフランクフルトのように大都市の公社が巨額の投資で域外も含めた再エネ電源を確保している例もあります。
特に**ミュンヘン市(バイエルン州)**のシュタットベルケ(SWM, Stadtwerke München)は、ヨーロッパ最大規模の公営ユーティリティ企業であり、再生可能エネルギーへの大胆な投資で知られます。SWMは2008年に「再生可能エネルギー拡大戦略」を打ち出し、2025年までにミュンヘン市全世帯の電力消費相当量を自社の再生可能エネルギー設備で生産するという目標を掲げました。この目標達成のため約90億ユーロの予算を投じ、北海の大型洋上風力発電所(グローバル・テックⅠやグウィント・ヤ・モール、ダンティス克など)に出資したり、地元周辺の水力・太陽光・地熱発電プロジェクトにも積極的に参画しています。こうした取り組みにより、ミュンヘンは世界でも有数の再生可能エネルギー都市を目指しており、SWMはその実現を担う中心的存在です。
また、多くのシュタットベルケは地域のエネルギー利用効率化にも貢献しています。スマートグリッド技術やスマートメーターの導入による需給調整、新しい蓄電システムやパワー・トゥ・ヒート/ガスといったセクターカップリングの実証にも、地方公社が積極的に関与しています。例えばアーヘン市のシュタットベルケ (STAWAG) は隣国ベルギーとの国境地域で先進的なスマートグリッド実験を行い、また中部ヘッセン州のヴォルフハーゲン市では市民の出資協同組合と提携して100%再生可能エネルギー電力供給を達成しました。このような市民参加型のプロジェクトでは、住民がシュタットベルケの太陽光発電パークに直接投資し、利益配分に関与する仕組みも生まれています。シュタットベルケが地域の再エネ事業プラットフォームとなることで、住民のエネルギー意識向上や利益の地域還元が実現し、持続可能な地域経営に繋がっています。
総じて、現代のシュタットベルケは単なるインフラ供給者に留まらず、環境目標や持続可能性戦略の重要な推進主体となっています。再生可能エネルギーへの転換、エネルギー効率化、地域循環経済の構築といった課題に対し、地域に根ざした公営企業である強みを活かして先進的な取り組みを行うことで、ドイツ全体の脱炭素化に寄与しているのです。
6. 代表的なエポックメイキング事例(ハンブルク、ミュンヘン、ウルム、ライプツィヒ等)
ここでは、ドイツのシュタットベルケの中でも特徴的な事例をいくつか取り上げ、その歴史的・現代的意義を概観します。
- ハンブルク(Hamburg): ドイツ第二の都市ハンブルクは、公営事業の再公営化を市民が成し遂げた例として注目されます。1990年代にエネルギー事業の大部分を民営化し、一時は北ドイツ電力会社(HEW)がヴァッテンフォール社の傘下に入っていました。しかし前述の通り2013年の住民投票で再公営化が決定し、電力・ガス・地域暖房の各ネットワーク運営権を市が買い戻しました。これによりハンブルク市はHamburg Energie(電力・ガス小売や再エネ発電を担う公社)や送配電事業会社を傘下に持ち、発電から配電まで統合的に運営できる体制を構築しています。再公営化後、ハンブルクの電力網事業は黒字を計上し市財政に貢献しているほか、行政が主体となって石炭火力発電所の段階的閉鎖や水素エネルギー実証プロジェクトなど野心的なエネルギー政策を進める下地となりました。ハンブルクは地方政府が公共サービスを取り戻し、気候目標(2030年までに1990年比排出半減・石炭熱供給ゼロ)を掲憲にまで明記した例であり、グローバルにも「都市による脱民営化」潮流の先駆けとして知られます。
- ミュンヘン(München): ミュンヘン市のシュタットベルケ(SWM)は、その規模と再生可能エネルギー投資で突出した存在です。SWMは市が100%出資する有限会社(GmbH)で、電気・ガス・水道・公共交通・通信など多岐にわたるサービスを提供しています。1998年に組織形態を公法から私法(GmbH)に変更しつつも、市が完全所有する点は維持し、経営の柔軟性と公共性を両立させています。SWMは2008年以来、大型の再生可能エネルギー投資プログラムを展開しており、前述のように2025年までに市の全電力消費相当を自社の再エネでまかなう計画です。既に北海の洋上風力発電所や地域の地熱発電所への出資を通じて目標の大半を達成しつつあり、ミュンヘンは世界初の人口百万都市で100%再エネ電力を実現する都市になると期待されています。加えてSWMは地下鉄・トラム・バスを運営する交通会社(MVG)も子会社に持ち、都市交通の電化や電力供給との統合に取り組んでいます。ミュンヘンのケースは、シュタットベルケが巨大都市インフラを包括的に担い、収益を都市政策(気候変動対策や公共交通改善)に再投資している好例です。利益の地域還元やサービス多角化というシュタットベルケの強みを最大限に発揮し、「持続可能な都市経営」の柱となっています。
- ウルム/ノイウルム(Ulm/Neu-Ulm): バーデン=ヴュルテンベルク州ウルム市とバイエルン州ノイウルム市にまたがる**シュタットベルケ・ウルム/ノイウルム(SWU)**は、複数自治体が共同で出資・運営する広域公営企業の例です。SWUはウルム市が94%、隣接するノイウルム市が6%を出資する形で設立された公社で、電力・ガス・地域熱供給・上下水道・公共交通・通信(光ファイバー網)など幅広い事業を展開しています。特徴的なのは、SWUが周辺の中小自治体とも協力関係を築き、新たな合同シュタットベルケを設立することで地域全体のサービス提供を拡大している点です。例えば近郊町村との合弁で送配電会社を立ち上げたり、郡部向けの電力小売会社を共同設立するといった取り組みを通じ、ウルム都市圏を越えた広域インフラ事業ネットワークを形成しています。SWUはまた、通信分野にも早くから参入し、地方で高速ブロードバンド網を提供する先駆けとなりました。財務面でも安定しており、2017年時点で連結売上高20億ユーロ超・従業員約1,700人を擁する大企業に成長しています。ウルム/ノイウルムの事例は、シュタットベルケの組織形態が単一都市に留まらず、地域連携によって柔軟に拡大しうることを示しています。州境を越えた自治体協働、公企業の経営効率化と多角化という観点でエポックメイキングな存在と言えるでしょう。
- ライプツィヒ(Leipzig): ライプツィヒ市のシュタットベルケ(ライプツィヒ市営企業)は、19世紀中頃に遡る長い歴史を持ち、東ドイツ地域における成功例として知られます。1840年にガス灯照明会社として創設された同社は、1913年にはドイツ初期の地域暖房(発電所の余熱を公衆浴場へ供給)も開始するなど、当時から先進的な都市インフラ事業を展開していました。東西ドイツ統一後、ライプツィヒのシュタットベルケは旧東側都市の中でいち早く市場経済に適応し、1990年代半ばに最新鋭のガス・蒸気コンバインドサイクル発電所を建設、2000年にはドイツの電力取引所(EEX)がライプツィヒに開設される中で電力取引にも参画しました。さらに2004年以降、バイオマス発電・バイオガス・風力・太陽光など再生可能エネルギーへの投資を拡大し、電力・熱供給の低炭素化に尽力しています。ライプツィヒ市営企業は現在も市が100%出資するGmbHであり、約1,700人の従業員と年商20億ユーロ超の規模を維持しつつ、年間3000万ユーロ以上を地域インフラ投資に充てています。この利益は市予算への繰入や設備更新に使われ、地域経済への付加価値創出に寄与しています。ライプツィヒの事例は、旧東独におけるシュタットベルケ復興の成功モデルであり、長い歴史を持つ公営企業が時代の要請に合わせて進化し続けている点で特筆されます。
7. 組織形態・法制度・財政構造・サービス分野の多様性
ドイツのシュタットベルケは、一口に公営企業と言ってもその組織形態やサービス範囲は多種多様です。法制度上、「シュタットベルケ」という語は正式な法律用語ではありませんが、一般には自治体(都市や基礎自治体)が出資・所有する公益事業体を指し、法的形態としては公法上の組織にも私法上の会社形態にもなり得ます。
組織形態の多様性:シュタットベルケは各自治体の事情に応じて様々な形で組織されています。伝統的には、市の一部局として運営される「公営企業体(Eigenbetrieb)」「直営事業(Regiebetrieb)」の形もありましたが、現在では多くが民間会社型の法人(有限会社=GmbHや株式会社=AG)として設立されています。これは、経営の迅速化・専門性向上を図るために私法形態を採用しつつ、株式の100%を自治体が保有することで公共性を担保する狙いがあります。例えばシュタットベルケ・ケルン(ケルン市)は持株会社方式を採用し、親会社(市が全株保有)が電気・ガス・水道など複数の事業子会社を傘下に収めています。
一方、地域によっては複数の自治体が共同出資する組合的企業(Zweckverband)や、都市と民間が合同出資する合弁会社になっている場合もあります。後者の例として、ベルリンのガス会社GASAGは株式の過半を民間エネルギー企業が保有していますが、それでも都市サービスを提供するという実態からシュタットベルケの一員と見なされています。要するに、シュタットベルケのガバナンス構造は一様ではなく、純然たる市役所の一部から民間資本混在型までグラデーションがあります。ただし共通するのは、最終的な意思決定に自治体(市議会や首長)が関与し、公共目的を掲げて運営される点です。
財政構造と経営:シュタットベルケは公共性を持ちながらも企業として収益を上げることが求められます。大半のシュタットベルケは利用料金収入で運営費を賄い、利益が出ればそれを将来の投資や自治体財政への繰り入れに充てています。近年の統計では、中規模以上のシュタットベルケはほぼ全て黒字経営であり、その利益は上下水道や公共交通といった不採算部門の赤字補填(クロスサブシディ)に用いられたり、配当金として自治体に納付されて市民サービス全般の財源になったりしています。自治体にとってシュタットベルケは財政上も重要な位置づけで、安定配当や税収入(法人税・事業税)をもたらす存在です。また、公営企業であるがゆえに長期的な視点で地域インフラ投資を行いやすく、利益第一の民間企業では躊躇するような大型設備更新や環境投資も積極的に実施してきました。例えばシュタットベルケ全体では年間80億ユーロ以上を設備投資に充てており、老朽管路の更新や電気自動車充電網の整備など、地域の将来に資する支出を続けています。財務面では自治体からの出資金や利益剰余に加え、必要に応じ地方公社債の発行や銀行融資で資金調達することもあります。ただしドイツでは地方債の管理や自治体企業の借入れは州の監督下にあり、過度な債務拡大を抑制する仕組みが整えられています。このような健全経営の枠組みの下、シュタットベルケは公共性と企業性を両立させる独自の財政構造を発達させてきました。
サービス分野の多様性:シュタットベルケが提供するサービス領域も都市によって異なりますが、典型的には以下のような分野があります。
- エネルギー供給(電気・ガス・熱供給):ほぼ全てのシュタットベルケが関与する中核分野です。発電・購入電力の小売、配電網の運営、ガス導管網の管理、地域暖房プラントの運営などを担います。近年はエネルギー効率コンサルティングや需要家とのエネルギーサービス契約(ESCO事業)なども手掛けるようになっています。
- 上下水道:水道水の供給と下水処理も伝統的に自治体の必須業務であり、多くのシュタットベルケが担当します。水源の保全、水質管理、下水インフラ維持まで幅広く関与し、高品質の水供給を支えています。ドイツでは上下水道は民営化されず公的運営が維持された分野で、シュタットベルケがその主体です。
- 公共交通:市内バス、路面電車、地下鉄などの運営は、大都市ではシュタットベルケの子会社または関連会社が担う例が多いです。小〜中規模都市では独立の交通公社を設けることもありますが、ウルムやライプツィヒ、ミュンヘンのようにエネルギー公社が交通部門も抱えるケースもあります。公共交通は収益性が低く補助が必要な分野ですが、シュタットベルケのエネルギー事業利益で赤字補填することで維持されている都市も少なくありません。
- 廃棄物処理・地域環境サービス:ごみ収集・処理、リサイクル事業、地域清掃などは都市によって担当が分かれますが、一部シュタットベルケは廃棄物焼却発電施設を運営し、エネルギー部門と連携しています。また除雪や公園管理など環境サービスを包含する公社もあります。
- 通信・IT:近年、新たな領域として台頭しているのが通信事業です。多くのシュタットベルケが光ファイバー網の敷設やインターネット・ケーブルテレビサービス提供に乗り出しています。民間通信事業者が敬遠しがちな地方部でのブロードバンド整備を、公営事業がリスクを取って進めているケースもあります。例えばミュンヘンのSWMは子会社M-netを通じて地域光ネット網を構築し、ウルムのSWUも市内全域に光通信を提供しています。これは現代版の「公共インフラ」として通信を位置づけた戦略と言えます。
- その他の公共サービス:シュタットベルケによっては、都市の駐車場経営、港湾・運河管理、地域住宅会社の運営、病院や文化施設の維持など、多様な業務を担う場合もあります。これらは都市ごとに事情が異なりますが、要はシュタットベルケという仕組みが「地域のニーズに応じて何でもこなす」柔軟な公企業として機能していることを意味します。例えばフランクフルト市のシュタットベルケ(Mainova)は図書館やプールなど文化施設の管理も行い、シュタットベルケ・ケルンは地域住宅会社を傘下に持つなど、サービス分野は多岐にわたります。
このように、シュタットベルケの組織・制度・財政・事業は千差万別ですが、それぞれの地域事情に合わせた形態で住民サービス提供の役割を果たしています。法制度的には各州の自治体法の下で運営されますが、重要なのはその使命が一貫して「公益(öffentlicher Zweck)の追求」にあることです。
営利企業であっても、民間が十分提供できない場合に限って自治体が経済活動を行うという補完性原則に立ち、地域住民の生活を支えることが目的である点で、シュタットベルケは他の民間企業と一線を画しています。この公共使命とビジネスのバランスこそ、シュタットベルケの多様性を貫く共通理念と言えるでしょう。
8. シュタットベルケの地域経済・地域ガバナンスへの影響
シュタットベルケは、その存在自体が地域経済とガバナンス(統治)に大きな影響を及ぼします。まず経済的側面では、シュタットベルケは地域に雇用と投資をもたらす重要なプレーヤーです。全国のシュタットベルケを代表する業界団体VKU(ドイツ地方公益事業協会)によれば、それら加盟企業は合計で約24万5千人を雇用し、年間売上高は1,100億ユーロを超え、年間投資額も85億ユーロに上ります。
個別の都市でも、公営事業体は往々にして有数の大雇用主であり、地域の中小企業にとっても主要な発注者です。シュタットベルケが支出する人件費や設備投資の多くは地元に落ちるため、地域内での経済波及効果が高く評価されています。実際、シュタットベルケが稼ぎ出す売上1ユーロあたり約0.5ユーロが、その地域内に付加価値として留まるという試算もあります。
これは、収益が地域の従業員給与や地元企業への発注、自治体への配当・税収入として還元されるためで、民間大企業に利益が吸い上げられる場合と対照的です。
例えばソーリンゲンやヘーメといった都市のシュタットベルケでは、収入の約48~55%が地域内に再投資・消費されており、地域経済の循環に寄与しています。
自治体財政の観点でも、シュタットベルケは重要な存在です。多くの公営事業は毎年利益の一部を市に納付しており、これは自治体の一般会計を潤す財源となっています。加えて、電力やガスの配電網運営にはコンセッション(特許使用料)収入が自治体にもたらされます。大都市では公社から数千万ユーロ規模の配当金が支払われ、これが学校や福祉など他分野の財源に充てられることもあります。
言い換えれば、シュタットベルケが健全経営であればあるほど、その都市の財政基盤も強化され、住民サービス全般の充実に繋がるのです。逆に公社が民営化されれば、配当や手数料といったお金は株主や民間企業に流出し、地域外へ富が移転してしまいます。
そのため、多くのドイツ市民は「シュタットベルケの利益は地元に残る」ことを支持し、公営事業への信頼感を持っています。
地域ガバナンス(統治)においても、シュタットベルケの影響は大きいです。地方自治体が自前の公企業を持つことで、エネルギー・水道・交通といった生活基盤について自ら意思決定できる範囲が広がります。自治体首脳や議会は公社の監督評議会にメンバーを送り込み、経営方針に関与しますし、重要事項は議会の承認事項とされ民主的統制が及びます。
これにより、地域の政治目標(例:気候変動対策や料金体系の是正、低所得者への配慮など)を公企業の事業計画に反映させやすくなります。実際、近年多くのシュタットベルケが再生可能エネルギー転換を進めたのも、自治体レベルでの気候目標設定と歩調を合わせた結果です。
また、公営企業は情報公開や住民への説明責任を負うため、民営企業に比べ透明性が高い傾向にあります。経営トップの人事も市議会で議論され、不祥事があれば議会で追及可能です。住民が直接関与する場面もあり、ハンブルクやベルリンのように住民投票で公社のあり方が問われることもありました。
このようにシュタットベルケは、地方自治の一部として地域コミュニティの意思を反映しやすい仕組みとなっています。
さらに、シュタットベルケは地域の長期的ビジョンを実現する手段として機能します。民間企業は短期の利益や株主価値を重視しがちですが、公営企業であれば社会的便益や長期投資を重視できます。例えば環境に優しいが採算性に劣る事業(例:水素インフラ整備、過疎地への公共交通維持など)にも、シュタットベルケならば地域の将来のために踏み切れる場合があります。その結果、地域として望ましい方向性(持続可能性や包括的サービス提供)が守られやすいという利点があります。
最後に、シュタットベルケは住民にとって身近な存在であり、地域アイデンティティの一部ともなっています。多くのドイツ人が自分の街の公社を信頼し、そこから電気や水を買うことに誇りや安心感を持っています。シュタットベルケのロゴが入ったバスに乗り、地元の水道水を飲み、冬には公社の除雪車が道路を清掃する――そうした日常の中で、公営企業は市民生活に溶け込み、地域の一体感を醸成しています。これはガバナンス面でも重要で、住民の支持と協力を得やすいことは、新たな施策(スマートメーター設置や節電キャンペーン等)の受け入れにもプラスに働きます。
以上のように、シュタットベルケは単なる公共サービス提供者に留まらず、地域経済を活性化し、自治体財政を潤し、民主的なガバナンスを下支えする多面的な役割を果たしています。その存在は「地方自治の経済的基盤」とも言え、ドイツにおける持続可能な地域社会の構築に欠かせない要素となっているのです。
【参考文献】 本稿作成に際し、以下を参照しています。
repository.kulib.kyoto-u.ac.jp