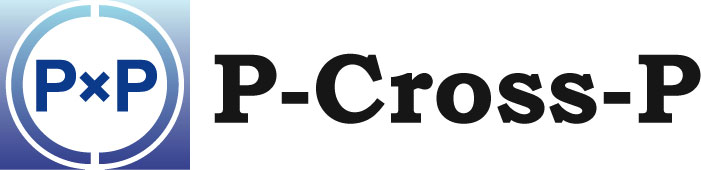公共経済学の系譜
PPP/PFIの理論的背景となる公共経済学について、その系譜をChatGPT(Deep Serch)で整理してみました。
質問: 公共経済学の系譜について整理してください。PPP/PFIとの関連を意識しつつ、日本を含む国際的な視点で、浅く広くカバーする形で整理してださい。
ChatGPT:
公共経済学(公共財政学)は、政府と市場の関わりや公共部門の経済活動を扱う経済学の一分野です。その理論は経済思想の発展とともに変遷してきました。以下では、歴史的な時代区分ごとに主要な理論や学説の系譜を整理します。各時代で公共財・外部性・市場の失敗・政府の役割に対するアプローチがどのように変化したかを概観し、近年注目されるPPP(Public-Private Partnership)やPFI(Private Finance Initiative)への理論的背景も含めて説明します。
古典派経済学の時代(18~19世紀)
古典派経済学の時代には、市場の自律性と政府の役割の最小化が強調されました。経済は「見えざる手」によって調和的に秩序づけられると考えられ、政府は防衛や治安維持、公共事業など限られた任務のみを担うべきだとされました。この時代には近代的な租税論や財政学の萌芽も見られますが、基本的には小さな政府観が支配的でした。
- アダム・スミス – 古典派の祖であり、著書『国富論』(1776年)で経済的自由放任を主張しました。スミスは政府の役割を「国防」「法と秩序の維持」「公共事業や公共機関の整備」に限定し、それ以外で市場に介入すべきでないと論じましたadamsmith.org。例えば民間では採算が取れないが社会全体に有益な道路・橋梁などのインフラは政府が供給する必要があるとしました。
- デヴィッド・リカード – 古典派を代表する経済学者で、自由放任(レッセフェール)の支持者でした。彼は経済における政府の役割は極力限定すべきであると考え、課税も必要最小限にとどめるべきだと主張していますtcd.ie。リカードは税の帰着(租税の負担が最終的に誰に及ぶか)について分析し、租税制度の設計に貢献しましたが、基本的立場は政府支出を抑え市場の効率に任せるというものでした。
- ジョン・スチュアート・ミル – 19世紀中期の経済学者で、古典派の流れを汲みつつも累進課税の正当化など政府の所得再分配機能にも言及しました。ミルは『経済学原理』(1848年)で課税の効率と公平の原則を論じ、租税は社会全体の利益のために用いられるべきだと述べています。一方で政府による市場介入には慎重で、基本的には個人の自由な経済活動を尊重する立場でした。
なお19世紀後半には、ドイツの経済学者アドルフ・ワグナーが「国家活動の拡大法則(ワグナーの法則)」を提唱し、経済発展に伴い公共支出のGDP比が高まる傾向を指摘しました。これは産業化・都市化により政府が担うべき機能(教育・福祉・インフラ整備など)が増大するという実証的な主張であり、古典派的な小さな政府観に一石を投じるものでした。
厚生経済学の展開(19世紀末~20世紀前半)
19世紀末から20世紀前半にかけて、経済学は「厚生経済学」の時代へ進みます。限界革命により経済分析における効用概念が確立されると、市場のもたらす効用を評価しつつ、必要に応じて社会全体の厚生(ウェルビーイング)を改善する方策が議論されました。この時代には市場の失敗(market failure)という概念が明確化され、公的介入の理論的根拠が整備されていきます。公共財の概念や外部性への対処法も徐々に発展しました。
- ヴィルフレド・パレート – イタリアの経済学者パレートは、厚生経済学において他者の効用との比較を経ずに効率性を評価する基準としてパレート最適の概念を確立しました。彼は1906年にパレート効用曲線を用いて、ある資源配分が他の誰の状況も悪化させずにこれ以上誰かの厚生を高められないとき、その配分は効率的(パレート最適)であると定義しました。この考え方は政府が介入する判断基準として、「より効率的な状態が存在するなら介入の余地がある」という形で理論的基盤を提供しました。またパレートは所得分配の不平等にも関心を寄せ、富の分布に関するパレート分布やローレンツ曲線の分析を残しています。
- アルフレッド・マーシャルとA.C.ピグー – ケンブリッジ学派のマーシャル(1890年代)とその弟子ピグーは、市場の外部性(外部効果)の概念を発展させました。マーシャルはある経済主体の行動が第三者に及ぼす副次的影響(外部効果)に着目し、特に産業の集積による外部経済などを論じました。ピグーは著書『厚生経済学』(1920年)で私的費用と社会的費用の乖離に言及し、企業の活動がもたらす外部不経済(公害など)の存在下では市場均衡が社会的最適にならないことを示しましたtcd.ie。そして政府が税(金銭的負担)や補助金を用いて外部性を是正すること(ピグー税)を提唱し、環境税や補助金政策の理論的基礎を築きました。このマーシャル=ピグーの分析は、「市場の失敗」に対処して社会全体の厚生を高めるという公共経済学の中心的課題を形作りました。またピグーらの研究から、恩恵が広く行き渡り個別には対価を徴収しにくいサービスの存在、すなわち公共財の概念も発展しましたtcd.ie。
- クヌート・ヴィクセルとエリック・リンダール – スウェーデンの経済学者ヴィクセル(1896年)は、それまでの古典派の前提とは異なり政府による所得再分配や価格統制によって社会全体の満足度(厚生)を高められる場合があることを指摘しましたtcd.ie。彼は富裕層と貧困層の間で所得移転を行えば総効用が高まる可能性を論じ、最低賃金や労働時間の規制といった政府政策を支持しましたtcd.ie。またヴィクセルは公共支出と課税の決定に関する新たな原則を提案し、単純多数決ではなく全会一致ルールによる合意形成で公共財を供給すべきだと主張しました。これは全員が受益に見合った負担を受け入れる形でなければ公共支出は行えないという考えで、公共財供給の合意メカニズムとして画期的でした。弟子のリンダール(1919年)はこの考えを発展させ、各個人が自分の受け取る公共財の便益に応じて異なる税額(価格)を支払う均衡概念(リンダール均衡)を示しました。リンダール均衡は理論上は公共財を効率的かつ公平に供給する解として注目され、後の公共財の経済学の基礎となりました。ヴィクセルとリンダールの業績により、公共財は経済学的に定義され分析できる概念となり、政府の財政活動(課税と支出)を厚生の観点から捉える理論が整備されました。
- 厚生経済学の基礎付け – この時代には他にもフランスのデュピュイ(1844年)が費用便益分析の嚆矢となる消費者余剰の概念を用いた公共事業評価を行い、イギリスのエッジワース(1881年)は無差別曲線を導入して効用の測定や公平の問題を分析しました。またアメリカのヘンリー・ジョージは土地税による公共財供給を唱えるなど、公共経済に関する多様な思想が生まれています。総じて19世紀末~20世紀初頭の厚生経済学の展開期には、市場の失敗(externalityや公共財)を是正し社会全体の効用を高めるための政府の役割が理論的に正当化され、租税による所得再分配や公共サービス提供の考え方が深化しました。
ケインズ革命と戦後の公共経済学(20世紀中葉)
1930年代の世界大恐慌を契機に、ケインズ革命と呼ばれる経済学のパラダイム転換が起こりました。ジョン・メイナード・ケインズは『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)において、有効需要の不足が不況の原因となり得ることを示し、政府が積極的に財政支出や減税を行って需要創出することで失業を削減できると主張しました。これは従来の古典派が信じた市場の自己調整に疑問を投げかけ、政府による経済への積極介入を正当化する理論的支柱となりました。ケインズ革命以降、公共経済学にも大きな影響が及び、政府の役割に対する考え方が拡張されました。
- ケインズ経済学の登場 – ケインズの理論は従来の常識を覆し、政府は景気安定化のため財政政策を積極的に用いるべきと説きました。彼は古典派の下では総需要が不十分になり得ること、完全雇用を維持するためには政府が不足する需要を補填する必要があることを示しましたtcd.ie。具体的には、完全雇用を達成する3つの方策(財政支出の増加とそれに伴う赤字、公債発行を伴う減税、均衡予算下での支出拡大)を提示しtcd.ie、不況期には赤字を恐れず公共投資などで需要喚起すべきと論じたのです。このケインズ革命により、多くの国で景気対策としての公共支出拡大や雇用創出プログラム(例:米国のニューディール政策)が採用され、政府のマクロ経済管理(安定化機能)が公共経済学の重要な柱となりました。
- 戦後の財政学(厚生国家の形成) – 第二次世界大戦後、経済復興とともに各国で福祉国家の理念が広まり、政府の経済への関与が制度的にも高まりました。アメリカの経済学者リチャード・マスグレイブは著書『財政の理論』(1959年)において、政府の経済的機能を「資源配分」「所得再分配」「経済安定」の三つに体系化しました。これは、政府は市場の失敗を補正して効率的な資源配分を行い(例:公共財の提供や外部不経済への対処granthaalayahpublication.org)、税制や社会保障によって公平な所得再分配を図り、さらに景気変動に対して財政・金融政策で景気安定化を図るという枠組みですgranthaalayahpublication.org。マスグレイブの理論は各国の財政運営の基本原則に大きな影響を与え、実際に戦後は多くの国で累進税制の強化や社会保障制度の拡充が行われました。日本においても戦後復興期から高度経済成長期にかけて、政府が積極的に産業基盤整備や社会資本投資を行い、教育・医療・年金などの社会保障制度を整備しています。これらは市場だけに任せず政府が経済発展と国民福祉に関与した例と言えます。
- 公共財理論の確立 – 戦後、公的財政の分析はさらなる理論的洗練が進みました。ポール・サミュエルソンは1954年の論文「純粋公共財の理論」において、公共財を非競合性(誰かが消費しても他の人の利用可能量が減らない)と非排除性(対価を支払わない人を消費から排除することが困難)という特性で定義しました。これは公共財を初めて明確に定義づけたもので、公共財供給におけるフリーライダー(ただ乗り)問題を指摘し、純粋公共財は市場では十分供給されないため政府提供が望ましいと結論づけました。このサミュエルソンの公共財理論は、その後の公共経済学の基盤となり、政府の資源配分機能を正当化する標準的理論となっています。また同時期に行われた費用便益分析の手法確立(MarglinやArrow他の貢献)により、公共事業や政策の社会的な費用対効果を計測して判断する枠組みも整いましたtcd.ie。これにより公共プロジェクトの評価に経済学的手法が導入され、インフラ投資や規制の是非を定量的に分析できるようになりました。
- 社会的選択と経済政策 – 厚生経済学が進む中で、民主的意思決定と厚生の関係も論じられるようになりました。ケネス・アローは『社会的選択と個人的評価』(1951年)でアローの不可能性定理を示し、複数人の選好を集約して社会的厚生順序を作ることの困難を証明しました。これは、合理的な条件を満たす投票決定方式は存在しないという衝撃的な結果で、どのような制度でも完全に公平・効率な社会的選択はできない可能性を示唆するものです。この理論は政府の意思決定プロセスを経済学的に捉える試みであり、後の公共選択理論にもつながりました。またダンカン・ブラックやアントニー・ダウンズによる多数決モデル分析、投票者行動の経済分析なども1950年代から始まり、公共経済学における政治過程の分析が芽生えました。
- 市場の失敗と新たな視点 – 戦後の経済学では、従来のピグー的な政府介入論に対し、新たな視点からの研究も登場しました。特にロナルド・コースは1960年「社会的費用の問題」において、当事者間で明確な財産権が定義され交渉コストが十分低ければ、外部不経済であっても当事者同士の取引(契約)により問題が解決され得ることを指摘しましたgranthaalayahpublication.org。このいわゆるコースの定理は、市場が失敗する場合でも適切な制度(財産権の割当て)を設計すれば政府の関与なしに効率的解決が可能であるケースを示したものです。例えば環境汚染問題でも、被害者と加害企業が交渉して補償額を決めれば公的規制なしに解決しうると論じました。もっとも現実には交渉の費用や当事者数の問題でコースの定理の前提は厳しいのですが、この指摘により市場の失敗に対する制度的対応の重要性が認識され、外部性問題へのアプローチが多角化しました。
以上のように、ケインズ革命から戦後の公共経済学の時代には、政府の役割が従来の「夜警国家」的な最小限から大きく拡大し、景気対策や社会福祉の担い手として積極的な位置づけが与えられました。同時に公共財・外部性理論が確立され、市場の失敗に対処する政府の機能が理論的にも整備されました。ただし後半にはコースらによる政府介入への新たな批判的視点や、政治プロセス自体の分析も芽生えており、次の時代への布石が打たれていきます。
新古典派経済学と公共選択(20世紀後半)
1960年代以降、公共経済学は新古典派の復権と、それまであまり考慮されてこなかった政府の失敗に焦点を当てる新しい方向へと進みました。高度成長とインフレ、高揚する政府支出に直面した1970年代には、「大きな政府」への批判や市場メカニズムの再評価が起こり、経済政策もより市場原理を重視する流れが強まります。理論面では、公共選択理論の台頭により政府の内部を経済学的に分析する視点が確立し、また情報の非対称性を考慮した新たな政策設計理論も登場しました。この時期は、古典派以来の市場重視の考え方が現代的に復活しつつ、政府の役割を再定義する時代といえます。
- 公共選択学派の台頭 – ジェームズ・ブキャナンやゴードン・タロックらは『合意の経済理論(The Calculus of Consent)』(1962年)に代表される研究で、政治的意思決定を経済学の方法で分析する公共選択理論を発展させました。彼らは政府を社会全体の利益を自動的に実現する存在とはみなさず、政治家や官僚も自らの利得を追求する経済人であると仮定しましたgranthaalayahpublication.org。これにより、選挙や議会での票集めのために非効率な支出が行われたり、官僚組織が予算拡大を図る(ニスカネンの官僚制モデル)など、政府の失敗が分析対象となりました。公共選択学派はまた、利益集団によるロビー活動やレントシーキング(一部集団が利権を得るために社会全体にコストを課す行為)に注目し、こうした現象が公共政策を歪めることを示しました。これらの研究は1970年代以降の行政改革や規制緩和の動きに理論的裏付けを与え、政府の役割に対する過度な信頼を見直す契機となりました。
- 市場メカニズムの再評価(新古典派反革命) – マクロ経済学の領域では、1970年代にフリードマンらのマネタリスト(通貨主義)やロバート・ルーカスらの新古典派マクロ経済学が台頭し、ケインズ的な裁量政策への批判が高まりました。フリードマンは政府支出拡大がインフレを招くと警告し、市場に任せた長期的成長路線への回帰を主張しました。ルーカスは理論的に、人々は合理的に将来を予測するため裁量的な政策は無効化されやすい(ルーカス批判)と論じました。こうした考えを背景に、1980年代には米国レーガン政権や英国サッチャー政権のもとで減税や民営化、規制緩和が推進されました。日本でも中曽根政権期に国鉄・電電公社・専売公社の民営化が行われるなど、市場原理を重視し政府部門を縮小する政策が取られました。これは、新古典派の「小さな政府」志向が各国の政策に影響を与えた例と言えます。
- 外部性への新たなアプローチ – 前時代に登場したロナルド・コースの指摘(1960)は、その後の制度経済学や環境経済学に大きな影響を与えました。コースの議論から発展して、環境問題では排出権取引のように市場メカニズムを活用する政策手段が考案されました。これは政府が汚染許可枠を設定し企業間で売買させるもので、企業は自社の削減コストと市場価格を比較して効率的に汚染削減を行います。こうした制度は1980年代以降実際に導入され、1990年の米国SO₂排出権取引制度や京都議定書(1997年)での排出量取引メカニズムなどに結実しました。つまり、新古典派の時代には市場の力を利用して公共目的を達成するというアプローチが広がったのです。また、チャールズ・ティーボーは1956年の論文で、住民が居住地を選択すること(“足による投票”)で地方公共財の供給が最適化される可能性を示しました。これは自治体間競争により公共サービスも効率化され得るという示唆であり、地方財政の分析に市場原理を導入した先駆けでした。
- 情報の経済学と制度設計 – 1970年代には、情報の非対称性を考慮した新たな公共経済学の分析手法が登場しました。ジョセフ・スティグリッツらは市場の失敗の一因として情報の不完全性を指摘し、例えば保険市場の逆選択や信用市場のモラルハザードなど、政府が規制や介入で改善できる領域を示しました。一方、ジェームズ・ミラーリーズとウィリアム・ヴィックリーは最適課税理論を発展させ、政府が税を課す際に人々の勤労インセンティブを損なわずに再分配を図る問題を解析しました。ミラーリーズ(1971年)は個々人の稼得能力が観察できない条件下で所得税率を設計するモデルを示し、完全情報下とは異なる情報制約下での厚生最大化を導出しましたgranthaalayahpublication.org。ヴィックリーもオークション理論への貢献(1961年)などを通じてメカニズムデザイン(制度設計)の基礎を築き、両者は1996年にノーベル経済学賞を受賞していますgranthaalayahpublication.org。このように、新古典派の時代後半には市場だけでなく政策のデザインそのものに経済学的手法を用いる動きが強まりました。租税や社会保険の設計、規制のあり方について、インセンティブと情報の観点から分析する理論が整備され、政府の介入をより洗練された形で行う道が模索されました。
以上、20世紀後半の公共経済学は、一方で政府への批判的検討(政府失敗の分析)を深めつつ、他方で依然残る市場の失敗にどう対処するかについてはより巧妙な制度設計や市場の力の活用によって解決策を見出そうとする方向に進みました。古典的な自由放任と厚生経済学的介入の対立を乗り越え、政府と市場の最適な関与バランスを探る理論がこの時期に充実したと言えるでしょう。
現代の制度経済学・契約理論とPPP/PFI(1990年代~現在)
1990年代以降、公共経済学はさらに制度の設計や契約関係に焦点を当てる発展を遂げています。冷戦終結前後から世界的に市場原理の導入(民営化・規制緩和)が進む一方、政府は全てを市場に任せるのではなく有効に補完し、市場の失敗を的確に是正する手腕が求められるようになりました。新制度派経済学や契約理論の台頭により、政府と民間の協調やインセンティブ設計に関する理論が公共経済分野にも本格的に導入されています。その流れの中で、官民のパートナーシップによる公共サービス提供というPPP/PFIの手法が各国で広がりを見せました。
- 新制度派経済学の影響 – ロナルド・コースの取引費用や所有権の議論を受け継ぎ、オリバー・ウィリアムソンやダグラス・ノースといった新制度派経済学者は、経済パフォーマンスにおける制度(ルール・組織形態)の重要性を明らかにしました。ウィリアムソンは市場と企業(ヒエラルキー)のどちらを選ぶかは取引費用によって決まると分析し、政府の役割もまた取引費用次第で効率的形態(官営か民営か)が変わることを示唆しました。例えば、民間企業同士の契約では解決しにくい市場取引コストが高い分野では政府が直接供給した方が効率的ですが、逆に市場で取引できるなら政府が無理に関与する必要はないという考え方です。このような新制度派の視点は、1980~90年代に各国で行われた民営化や政府機関の市場化(ニュージーランドや英国の改革など)に理論的裏付けを与えました。またノースは歴史分析から、財産権を保障し取引を円滑化する制度が経済発展を促すことを示し、開発経済学やガバナンス論にも影響を与えています。新制度派経済学の教訓は公共経済にも取り入れられ、「政府対市場」という二分論ではなく、いかに制度をデザインすれば低コストで公共目的を達成できるかが重視されるようになりました。
- 契約理論とインセンティブ設計 – 1980年代以降に発展した契約理論(コントラクト・デザイン)は、公共部門における官民の関係にも適用されています。とくにオリバー・ハートやベンガト・ホルムストロームらの不完全契約理論・エージェンシー理論の成果は、政府が民間に業務を委託する際の契約設計や所有形態の選択に示唆を与えました。ハートらの研究investopedia.comは、契約では将来の不確実な事態をすべて規定できない(不完全契約)ため、誰が資産の所有権(残余支配権)を持つかで成果が変わることを示しました。例えば公共サービスにおいて、民営化すれば企業はコスト削減の強いインセンティブを持ちますが品質がおろそかになる恐れがある、一方、公営であれば品質は維持しやすいが効率が落ちる、といったコストと品質のトレードオフが存在します。ハート&シュライファー&ヴィシュニィ(1997年)の研究は刑務所運営を例に、サービスの質が重要な場合には政府所有が望ましいが、コスト効率向上が重視され品質低下の影響が小さい場合には民営化契約も有効と分析しました。この理論は各種の公共サービス(教育、病院、インフラ管理など)における官と民の役割分担を考えるフレームワークを提供し、どのような契約・所有形態が社会的厚生を高めるかを検討する基礎となっています。またエージェンシー理論では、情報の非対称性下で委託者(政府)と受託者(民間業者)との間のインセンティブの整合を取る契約の工夫が重視されますlink.springer.com。例えば成果連動型の報酬制度や、モニタリングと裁量のバランスを取った契約条項など、民間の効率性を活かしつつ公共の利益を確保する設計が議論され、現実のPFI契約書などにも取り入れられています。
- PPP/PFIの理論的背景と国際展開 – 上述のような制度・契約理論の進展を背景に、官民パートナーシップ(PPP)という手法が各国で広まりました。PPP/PFIは、公共インフラや公共サービスの提供において官と民が長期契約を結びリスクと役割を分担する協調関係です。民間の資金力・経営効率と、公的主体の公益性・規制力を組み合わせることで、従来の政府直営よりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供することを狙いますlink.springer.comlink.springer.com。PPPの具体形態としては、民間が施設を建設・運営し政府が一定期間利用料を支払うPFI(Private Finance Initiative)や、コンセッション(公共施設運営権の民間譲渡)など様々なスキームがあります。 このPPPの概念自体は1990年代にイギリスで本格化しました。イギリスでは1992年に保守党政権(メージャー首相)のもとでPFI制度が導入され、その後1997年以降の労働党政権でも公共サービス改革の柱としてPPPが推進されましたinvestopedia.com。PFIは施設の建設・維持管理を民間に任せ、政府はサービスの出来高に応じて支払いを行う方式で、病院・学校・道路など多数のプロジェクトに適用されました。イギリスでの成功(と失敗の教訓)を受け、PPP/PFIは欧州やアジアなど世界各国に広がりました。日本でも**1999年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)**が制定され、本格的にPFI手法が導入されましたlexology.com。以降、日本では空港運営や上下水道事業などでコンセッション方式のPPPが進められ、2019年度末までに740件超・総事業費6兆円超のPFI事業が実施されていますlexology.com。政府もPPP/PFI推進を成長戦略の一環と位置づけ、地方自治体に対してPPPの優先的検討を促すガイドライン策定(2015年)など制度整備を行ってきました。 PPP/PFIの成功には、適切な契約デザインと制度整備が不可欠です。契約期間が長期にわたるため、不確実な事態への対応条項やリスク分担の明確化が重要となります。また公共部門が最終的な責任を負う以上、民間に任せつつも公共目的が損なわれないようコントロール権を確保する必要がありますlink.springer.com。この点で契約理論・エージェンシー理論が示すような原理(インセンティブの付与とモニタリングのバランス)が活用されますlink.springer.com。例えば、サービス水準の客観指標を定め、それを満たした場合にのみ民間事業者へ報酬を支払う仕組みや、重大なサービス水準未達時には契約を終了できる条項などが設けられます。現代の公共経済学はこのように**「官か民か」ではなく「官と民をどう組み合わせるか」**という視点で発展しており、PPPはその象徴的な実践例と言えるでしょう。
- 現代的課題と公共経済学 – 21世紀に入り、公共経済学の射程はさらに国際的・学際的に広がっています。地球規模の公共財である気候変動問題では、各国政府の協調行動や国際制度の設計が重要課題となっており、経済学者は炭素税や排出権取引の効果分析を通じて政策提言を行っています。また行動経済学の知見を取り入れ、人々の認知バイアスを考慮した政策(ナッジ理論に基づく介入など)も試みられています。加えて、財政赤字の持続可能性や世代間公平の問題、グローバル化による税源移動(租税競争)への対応といった新たな課題にも、現代の公共経済学は取り組んでいます。国ごとの制度や政治状況を踏まえつつ、如何にして効率性と公平性を両立し社会的厚生を高める政策を設計するかが、引き続き公共経済学の中心的テーマとなっています。
参考文献:公共経済学の発展については、Margaret Doyle「The History of the Theory of Public Finance」tcd.ietcd.ieやMusgrave『財政の理論』、ならびに近年の公共選択・契約理論の文献granthaalayahpublication.orglink.springer.comなどを参照しました。また、日本におけるPFI制度の経緯については内閣府PFI推進室資料lexology.comを参照しています。
質問: 公共経済学における第三セクターの論評について日本を含む国際的視点で示してください。
ChatGPT:
公共経済学における第三セクター(Third Sector)は、政府(第一セクター)や市場(第二セクター)とは異なる、非営利組織や市民社会団体、協同組合などを指します。これらの組織は、公共サービスの提供や社会的課題の解決において重要な役割を果たしています。以下に、日本および国際的な視点から、第三セクターに関する公共経済学的な論評を概観します。
国際的視点:第三セクターの多様な役割と理論的枠組み
1. 非営利セクターの経済理論
国際的には、第三セクターは非営利組織(NPO)や市民社会組織(CSO)を中心に研究されており、以下のような理論的枠組みが提唱されています。
- 契約失敗理論(Contract Failure Theory):市場や政府が提供できないサービスを非営利組織が補完する役割を果たすとする理論。
- 公共財理論(Public Goods Theory):非営利組織は、政府や市場が十分に提供できない公共財を供給する役割を担うとする理論。
- ソーシャル・アントレプレナーシップ(Social Entrepreneurship):社会的課題の解決を目的とした革新的なアプローチを取る非営利組織の活動を指します。
これらの理論は、非営利組織の存在意義や機能を理解するための基盤となっています。
2. 国際的な研究とネットワーク
国際的な第三セクター研究の推進には、以下のような組織やプロジェクトが貢献しています。
- 国際第三セクター研究学会(International Society for Third-Sector Research, ISTR):1992年に設立され、世界中の研究者が第三セクターに関する知見を共有・発展させるためのプラットフォームを提供しています。
- ジョンズ・ホプキンス大学の比較非営利セクタープロジェクト(Comparative Nonprofit Sector Project):40カ国以上で非営利組織の経済的・社会的影響を比較研究し、第三セクターの国際的な理解を深めています。
日本における第三セクターの特性と課題
日本では、「第三セクター」という用語が特定の意味合いを持ち、地方自治体と民間企業が共同出資する事業体(いわゆる「第三セクター方式」)を指すことが一般的です。これは、公共性と民間の効率性を融合させることを目的としていますが、以下のような課題も指摘されています。
- 財政的持続可能性の問題:多くの第三セクター事業体が赤字経営に陥り、自治体の財政負担となっているケースがあります。
- ガバナンスの課題:官民の役割分担が不明確であり、意思決定の透明性や責任の所在が曖昧になることがあります。
これらの課題に対処するため、公共経済学の視点からは、ガバナンスの強化や財務管理の改善、民間資本の導入による効率化などが提案されています。
PPP/PFIとの関連性
第三セクターとPPP(Public-Private Partnership)/PFI(Private Finance Initiative)は、公共サービスの提供における官民連携の形態として関連しています。特に、日本においては、第三セクター方式がPPP/PFIの先駆的なモデルと位置づけられることもあります。しかし、第三セクター方式の課題を踏まえ、より明確な契約関係とリスク分担を特徴とするPPP/PFIの導入が進められています。
結論
公共経済学における第三セクターの研究は、国際的には非営利組織や市民社会の役割に焦点を当て、日本では官民共同出資による事業体の運営に関する課題に注目しています。今後、公共サービスの提供において、第三セクターの多様な形態とその効果的な活用方法について、さらなる研究と実践が求められます。